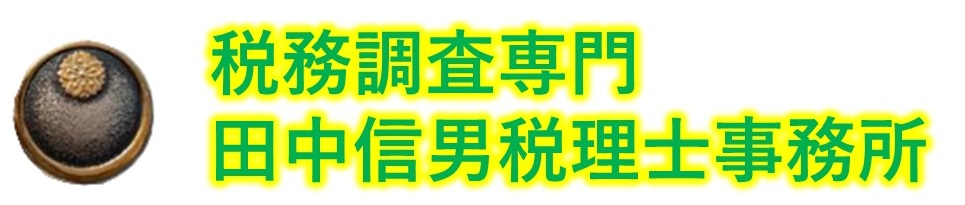税務調査における立証責任について
(2026年1月22日更新)
結論
・立証責任と税務調査の受忍義務、回答義務を混同してはなりません。
・久保憂希也書籍における「訴訟における立証責任」=「税務調査における立証責任」という考えに弊所は同意します。
・久保憂希也書籍における「納税者が不利な項目」=課税庁に立証責任「納税者に有利な項目」=納税者に立証責任という考えに弊所は同意します。
・令和4年(2022年)度改正によるR5年(2023年)以後の後出し簿外経費不可は立証責任の論点と密接に関係します。
・後出し簿外経費不可規定の創設などを考慮すれば「納税者が不利な項目」=課税庁に立証責任「納税者に有利な項目」=納税者に立証責任という考えが今後法的に明確化されると考えます
以下で詳細を記述します。
立証責任と税務調査の受忍義務、回答義務を混同してはなりません
ネットで「税務調査 立証責任」と検索すると、「立証責任は国税・税務署・課税庁側にある」という文章を目にすると思います。そうすると、売上漏れのチェックは税務署が勝手に原始資料からチェックすればよいのだ、交際費の経費性は税務署が勝手に調べればいいんだ、というような誤認が生まれる可能性があります。
しかし、納税者は税務調査に対する受忍義務、回答義務があります。税務署調査官からの税務調査に関する質問は協力して回答しなければなりません。非協力的な場合は、受忍義務違反といったような納税者に非が発生します。立証責任は、そのような意味ではございませんのでご注意ください。
久保憂希也書籍における「訴訟における立証責任」=「税務調査における立証責任」という考えに弊所は同意します
久保憂希也「元国税調査官が解説実例・判例で学ぶ税務調査の深奥」マトマ出版(2013年1月30日)p83-より
税務調査において、調査官から否認指摘を受けた項目について、立証責任は誰にあるのでしょうか。つまり、否認指摘をした課税庁(調査官)が否認をするための根拠・理由を立証しなければならないのか、もしくは、納税者側が否認指摘に対して反論するために、根拠・理由を立証しなければならないのか、本章はここが争点です。
まず、「立証責任」とは以下のような意味で使われます。なお、本章では「立証責任」で統一しますが、下記にある通り、「証明責任」「挙証責任」「説明責任」などの言葉も使われることがありますが、意味はすべて同じです。
証明責任とは、当該事実が立証されない場合に、訴訟の結果について不利益を受ける責任のことである。
(「税務訴訟の法律実務」188ページ参照)
つまり訴訟の場において、争い・論点となっていることを原告・被告のどちらがそれを証明するのか、それが「立証責任」の配分・分担の問題となるわけです。
さて、ここではいきなり訴訟の話か、と思われた方がいるかもしれませんが、税務調査はあくまでも訴訟を前提に行うものです。
実務上多くの場合、修正申告を提出することで税務調査が終了しますが、これはあくまでも、調査官の否認指摘に納税者が納得したからであって、納税者が納得できないのであれば、課税庁から(増額)更正をしてもらうしかありません。更正後にまだ納得できないのであれば不服申立ての手続きから裁判にいくしかないのです。つまり、税務調査は本来、課税庁側・納税者側の双方が訴訟までいくことを前提に行われるべきものなのです(実際に私が調査官時代、上司から常に訴訟を意識して調査を厳格にやるように教えられてきました)。
ということは、立証責任がどちらにあるのか、という問題に対しても、「訴訟だから」どちらに立証責任があるという問題ではなく、「訴訟における立証責任」=「税務調査における立証責任」なのです。
久保憂希也書籍における「納税者が不利な項目」=課税庁に立証責任「納税者に有利な項目」=納税者に立証責任という考えに弊所は同意します
久保憂希也「元国税調査官が解説実例・判例で学ぶ税務調査の深奥」マトマ出版(2013年1月30日)p83-より
では、税務調査においては、どんな場合でも「立証責任=課税庁」かというと、そうではありません。ここまで書いてきたとおり、調査官から否認指摘を受けた項目は、課税庁側に立証責任があります。しかし、稀なケースとして、納税者側に立証責任がある場合が存在します
立証責任が課税庁にあるのか、納税者にあるのかを分ける基準は、簡単に書くと下記のとおりです。
「納税者が不利な項目」=課税庁に立証責任
「納税者に有利な項目」=納税者に立証責任
調査官から否認指摘を受けた場合は、「納税者が不利」ですから、課税庁に立証責任があるというわけです。では、納税者に有利な項目としては、具体的にどのような項目があるのでしょうか。下記はあくまでも例ですが、税務調査で問題にあるのは、これらの項目が代表例でしょう。
【納税者に有利になる項目例】
・当初の申告で算入していなかった経費を税務調査で認めてもらう場合
・措置法適用による特別控除の項目
・圧縮記帳による損金計上項目
・課税庁が通達等で認める納税者に有利な税務処理の例外規定(資産の評価損失・短期前払費用)
・加算税の賦課に「正当な理由」があり、加算税が課されないことを主張する場合
・不当な税務調査を訴える場合
令和4年(2022年)度改正によるR5年(2023年)以後の後出し簿外経費不可は立証責任の論点と密接に関係します
こちらのページをご参考ください。
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
まとめますと、税務申告に対して不誠実な者が税務調査開始後に簿外経費を主張する場合は、不利な規定が明文化されました。
具体例:領収書等の証拠資料が不存在の場合にメモ書きで所得税法上又は法人税法上の経費と認められるかどうかの立証責任など
下記の表をご参考ください。
(表1)立証責任について申告済案件及び無申告案件
上記の表で改めて解説する点は下記となります。
・外注先が発行した100万円の領収書が存在せず納税者が作成したメモのみで現金払いであった場合の所得税法上及び法人税法上の経費計上可能性について
●申告済み案件の場合は、税務署側が立証責任を負い、補助的に納税者も負う、と解されます。
●無申告案件で令和4年(2022年)分以前は、納税者が立証責任を負うはずが税務署が負うという理不尽が存在した、と解されます。
●無申告案件で令和5年(2023年)分以後は、原則的にに後出し簿外経費否認規定より認められない、例外的に税務署が調査してくれれば認められることもある、と解されます。
まとめ
後出し簿外経費不可規定の創設などを考慮すれば「納税者が不利な項目」=課税庁に立証責任「納税者に有利な項目」=納税者に立証責任という考えが今後法的に明確化されると考えます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税原則課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します