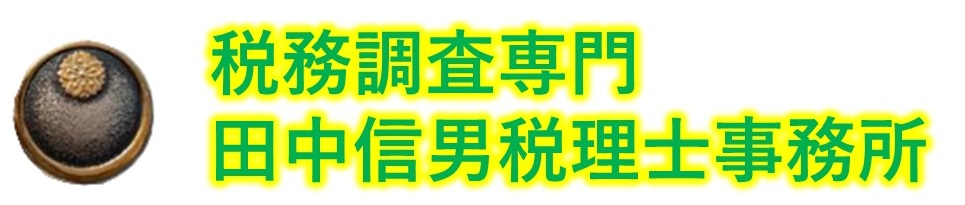税理士へ税理士報酬を支払って事前自主申告するメリットについて
(2026年1月18日更新)
結論
やましいことに心当たりがある場合には、どのようなケースにおいても税理士へ税理士報酬を支払ってでも事前自主申告する方がメリットがあるケースが多数と考えます。以下でパターンに分けて分析します。
・無申告者個人事業主の場合のメリット
・無申告者法人の場合のメリット
・やましいことに心当たりのある過少申告者個人事業主の場合のメリット
・やましいことに心当たりのある過少申告者法人の場合のメリット
無申告者個人事業主の場合のメリットを解説
◎無申告者個人事業主の場合のメリット
・事前自主申告しなければ無申告重加算税かつ7年分調査のところ無申告加算税かつ5年分調査で済む可能性が高い
・高額な無申告に対する無申告加算税の加重を防ぐことができる
・税務調査中に売上帳簿が無いことに対する無申告加算税の加重を防ぐことができる
・無申告状態のまま税務調査を受けた場合は、確かに存在したはずだが領収書等を紛失した経費は後橋簿外経費不可とされる可能性があるが、それを防ぐことができる可能性が高まる
・上記を考慮すると税理士報酬を支払って事前自主申告する方が結果として金銭的負担が減る可能性の方が高い
◎解説
弊所の仮説ですが、近年は無申告に関しても重加算税が賦課されかつ7年分調査となっていると分析しております。それは、近年は売上金が通帳に入金されておりうっかり無申告や失念による無申告であると言い逃れできず、意図的な無申告であるとの認定されるケースが増えてきているからと考えます。仮に過去7年間以上連続して売上除外等をしていれば、7分調査となります。しかしこれも弊所の現在の経験に基づく仮説ですが、過去7年間以上連続して売上除外等をしていても事前自主申告5年分すれば5年調査で済む可能性が高いです。
近年においては無申告に対する罰則化が進んでおります。しかし、事前自主申告すれば高額な無申告に対する無申告加算税の加重を回避することができ、調査開始後に売上帳簿不十分を指摘された場合の加重も回避することができ、後出し簿外経費不可も回避することができます。
そうすると税理士へ税務調査対応のための税理士報酬を支払ったとしてもトータルの負担としては安く済むケースの方が多いと推測します。根拠としましては以下のページをご参考ください。
無申告に対して重加算税は賦課されるのか及び増額更正期間は5年か7年かについて
高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしいというご要望は遺憾ながら対応困難ですが結果的にメリットのあるケースがほとんどです
無申告者法人の場合のメリットを解説
◎無申告者法人の場合のメリット
・事前自主申告しなければ無申告重加算税かつ7年分調査となるところ無申告加算税かつ5年分調査で済む可能性がある。高額な無申告加算税の加重を回避できる。売上帳簿不十分による無申告加算税の加重を防ぐことができる。後出し簿外経費不可を回避できる可能性がある。
・法人税申告書作成を税理士ではない知識のない方が自力で作成することは難易度が高いため代行してもらえる。
・役員報酬の計上を失念すると申告内容が不利になるが、その失念を防ぐことができる。
◎解説
法人を設立したうえでかつ売上金と思われる入金があるにも関わらず無申告である場合は、無申告重加算税が賦課される可能性は高いと考えます。弊所の現在の経験に基づく仮説ですが、過去7年間以上連続して売上除外等をしていても事前自主申告5年分すれば5年調査で済む可能性が高いです。また法人税申告書の作成は税理士でなければ難易度が高いと考えます。こららを考慮すると税理士へ依頼するしかないと言い切れるほど、メリットが大きいと考えます。根拠としては以下のページをご参考ください。
無申告に対して重加算税は賦課されるのか及び増額更正期間は5年か7年かについて
高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしいというご要望は遺憾ながら対応困難ですが結果的にメリットのあるケースがほとんどです
無申告法人は追徴本税がそもそも高額となりそれに伴い加算税も高額となる恐れがある
やましいことに心当たりのある過少申告者個人事業主の場合のメリットを解説
◎やましいことに心当たりのある過少申告者個人事業主の場合のメリット
・やましいことに心当たりがある場合は、事前自主申告しなければ重加算税かつ最大7年分調査のところ過少加算税かつ最大5年分調査で済む可能性が高い
・令和3年分以前の個人所得税修正申告5表(令和4年から廃止)作成はやや特殊であり知識が必要だが税理士に作成代行を依頼できる
・令和4年分以降の「申告書第一表」と「申告書第二表」を利用した修正申告を税理士に作成代行を依頼できる
・上記を考慮すると税理士報酬を支払って事前自主申告する方が結果として金銭的負担が減る可能性の方が高い
◎解説
やましいことに心当たりがある過少申告者についてはうっかりミスとして隠蔽仮装を否定することは困難と考えます。弊所の現在の経験に基づく仮説ですが、過去7年間以上連続して売上除外等をしていても事前自主申告5年分すれば5年調査で済む可能性が高いです。従って税理士報酬を支払ってでも税理士へ事前自主申告を含めた税務調査立会を依頼する方がトータルとして負担が減る可能性が高いです。また個人事業主の修正申告書の作成という恐らく納税者が慣れていないであろう作業を税理士へ代行できるメリットも大きいです。根拠としましては以下のページをご参考ください。
うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?
修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります
税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしいというご要望は遺憾ながら対応困難ですが結果的にメリットのあるケースがほとんどです
やましいことに心当たりのある過少申告者法人の場合のメリットを解説
◎やましいことに心当たりのある過少申告者法人の場合のメリット
・やましいことに心当たりがある場合は、事前自主申告しなければ重加算税かつ最大7年分調査のところ過少加算税かつ最大5年分調査で済む可能性が高い
・法人税修正申告作成は恐らく税理士でなければ完成させることができない
◎解説
やましいことに心当たりがある過少申告者についてはうっかりミスとして隠蔽仮装を否定することは困難と考えます。弊所の現在の経験に基づく仮説ですが、過去7年間以上連続して売上除外等をしていても事前自主申告5年分すれば5年調査で済む可能性が高いです。法人税の修正申告書を作成することは専門知識が必要となります。こららを考慮すると税理士へ依頼するしかないと言い切れるほど、メリットが大きいと考えます。根拠としては以下のページをご参考ください。
うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる?
修正申告書作成については通常の確定申告書作成とやや異なります
税理士報酬に見合う金額的メリットを必ず保証してほしいというご要望は遺憾ながら対応困難ですが結果的にメリットのあるケースがほとんどです
まとめ
・無申告者については無申告重加算税のリスク、無申告加算税の加重というリスクから税理士へ依頼して事前自主申告するメリットは大きいと考えます。
・やましいことに心当たりがある過少申告者については重加算税のリスクから税理士へ依頼して事前自主申告するメリットは大きいと考えます。
・法人については法人税申告書作成は専門的知識が必要とされることから税理士へ依頼しなければ事前自主申告はできないと言い切れるほどメリットは大きいと考えます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します