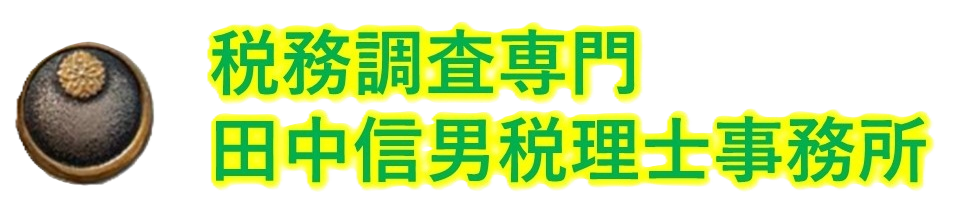税法における立証責任について
(2026年1月22日更新)
まず立証責任という言葉は裁判における文言であり、つまり税務訴訟以外の税務実務においてはあまり考える必要はないはずと思われます
立証責任の定義は下記となります。
立証責任(りっしょうせきにん)とは、裁判において、ある事実の真偽が不明な場合に、その事実を前提とする法律効果の発生または不発生によって、当事者の一方が被る不利益のことです。
したがって、この費用が経費になるかどうか立証責任がある、この税務申告書の作成の根拠においては納税者に立証責任がある、というような文章は誤用のように思われます。
しかしもし仮に国税と争った場合の立証責任はどちらにあるかと考えることは有益と解されます。
弊所は立証責任について理解することは有益と考えます。久保憂希也「元国税調査官が解説実例・判例で学ぶ税務調査の深奥」マトマ出版(2013年1月30日)p83より、
実務上多くの場合、修正申告を提出することで税務調査が終了しますが、これはあくまでも、調査官の否認指摘に納税者が納得したからであって、納税者が納得できないのであれば、課税庁から(増額)更正をしてもらうしかありません。更正後にまだ納得できないのであれば不服申立ての手続きから裁判にいくしかないのです。つまり、税務調査は本来、課税庁側・納税者側の双方が訴訟までいくことを前提に行われるべきものなのです(実際に私が調査官時代、上司から常に訴訟を意識して調査を厳格にやるように教えられてきました)。
ということは、立証責任がどちらにあるのか、という問題に対しても、「訴訟だから」どちらに立証責任があるという問題ではなく、「訴訟における立証責任」=「税務調査における立証責任」なのです。
弊所が考える税法における立証責任
弊所独自の見解ですが、税法における立証責任は下記が存在すると考えます。
・税務訴訟における立証責任について
・申告納税制度における立証責任について(税務調査を理解するために申告納税制度を理解しよう)
・税務調査における立証責任について(税務調査における立証責任について)
・重加算税賦課要件事実の立証責任について(重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について)
・後出し簿外経費における立証責任について(隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に)
下記で詳細を記述します。
税務訴訟における立証責任について
弊所は谷原誠書籍、久保憂希也書籍を参考とし、税務訴訟における立証責任は国税側であると結論づけました。
谷原誠「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」ぎょうせい(令和元年12月1日)p131-132より、
ところで、訴訟においては、主張立証責任という概念があります。これは、主張立証責任を負担する当事者が、法律上の要件(課税要件)に該当する事実を主張立証しなければならない。というものです。
要件事実の立証責任の分配については、判例では、法律要件分類説によるものが多いと言われています。法律要件分類説は、民事訴訟における立証責任の分配に関する通説です。行政処分の権利発生事実は行政庁が、権利障がい及び証明津事実は国民が立証責任を負うとする説です。取消しを求められた行政処分(更正)が法規を適用した行政処分であるときは、国が立証責任を負い、法規の適用を拒否した行政処分であるときは、国民が立証責任を負う、という説明もできます。
課税要件事実の立証責任は、納税者と課税庁とどちらが負担するかについて、最高裁判決は、所得税事案に関し「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決、月報9巻5号668頁)としており、課税要件事実の主張立証責任は課税庁にあるとしています。
久保憂希也「元国税調査官が解説実例・判例で学ぶ税務調査の深奥」マトマ出版(2013年1月30日)p83-より
立証責任とは?
税務調査において、調査官から否認指摘を受けた項目について、立証責任は誰にあるのでしょうか。つまり、否認指摘をした課税庁(調査官)が否認をするための根拠・理由を立証しなければならないのか、もしくは、納税者側が否認指摘に対して反論するために、根拠・理由を立証しなければならないのか、本章はここが争点です。
まず、「立証責任」とは以下のような意味で使われます。なお、本章では「立証責任」で統一しますが、下記にある通り、「証明責任」「挙証責任」「説明責任」などの言葉も使われることがありますが、意味はすべて同じです。
証明責任とは、当該事実が立証されない場合に、訴訟の結果について不利益を受ける責任のことである。
(「税務訴訟の法律実務」188ページ参照)
つまり訴訟の場において、争い・論点となっていることを原告・被告のどちらがそれを証明するのか、それが「立証責任」の配分・分担の問題となるわけです。
さて、ここではいきなり訴訟の話か、と思われた方がいるかもしれませんが、税務調査はあくまでも訴訟を前提に行うものです。実務上多くの場合、修正申告を提出することで税務調査が終了しますが、これはあくまでも、調査官の否認指摘に納税者が納得したからであって、納税者が納得できないのであれば、課税庁から(増額)更正をしてもらうしかありません。更正後にまだ納得できないのであれば不服申立ての手続きから裁判にいくしかないのです。つまり、税務調査は本来、課税庁側・納税者側の双方が訴訟までいくことを前提に行われるべきものなのです(実際に私が調査官時代、上司から常に訴訟を意識して調査を厳格にやるように教えられてきました)。
ということは、立証責任がどちらにあるのか、という問題に対しても、「訴訟だから」どちらに立証責任があるという問題ではなく、「訴訟における立証責任」=「税務調査における立証責任」なのです。
国税の論文に明記あり
ここまでを前提として、では結局、税務調査ではどちらに立証責任があるのかが問題になります。
立証責任を考えるうえで、非常に重要な論文が2つありますので、ぜひ要旨だけではなく、本文も読んでいただきたいと思います。
「税務訴訟における証明責任論の再構成」
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/141/hajimeni.htm
「税務訴訟における立証責任-裁判例の検討を通して―」
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/50/50//hajimeni.htm
この2つの論文は、国税庁(税務大学校)のホームページに載っているもので、国税職員が書いたものです。補足説明をしておくと、国税職員にはある決められた期間、税務大学校で研修を受けることになります。そこでは、卒業(研修の終了)時に論文を書かなければならないのです。それら論文の中で、優秀だと認められた論文だけが国税庁のホームページで公開されるのです(正式には論文ではなく、「論叢(ろんそう)」と呼ばれています)。上記に紹介したもの以外でも、非常に参考になる論文も数多くあるので、興味あるものだけでもぜひお読みください。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou.htm#back_no
さて話を戻すと、立証責任について書かれた2論文では、税務訴訟では原則的に、「立証責任=課税庁」となっています。
「税務訴訟における証明責任論の再構成」の「3 税務訴訟における証明責任(3)」には、以下の通り明記されています。
「学説の大多数は、以上のように、税務訴訟においては課税庁が証明責任を負担する、としているが、判例も「所得の存在およびその金額について決定庁が証明責任を負うことは、いうまでもないところである」(最判昭38・3・3税資37号171頁)と判示したものを代表として、課税庁に証明責任があるとするのが、判例の主流となっている」
私が調べてみた範囲では、立証責任を論じる学説の全部が「証明責任=課税庁」となっており、それに対する反論はありませんでした。主なものとしては、『税務訴訟の法律事務』(弘文堂)で、税務訴訟の専門弁護士である木山泰嗣弁護士も、税務調査における否認指摘にかかる立証責任は課税庁にあること、またその根拠と引用を明示しています。
立証責任を押し付けられたら
税務調査の現場では、調査官が否認指摘をしてきた項目に対して、「反論できなければ否認しますよ」などと言ってくるケースが多くありますが、これは明らかに間違いなのです。否認するための根拠・理由を探し、それを立証するのは調査官の役割なのです。
勘違いしていただきたくないのは、納税者側には調査官の質問に対する「回答義務(受忍義務)」がありますが、これは立証責任とは別問題です。調査官が帳簿・帳票類を精査した結果として質問をしてきた場合、納税者はその根拠となる原始帳票類が存在するのであればそれを提示しなければなりませんし、事実がわかるのであれば口頭でも説明をしなければなりません。
ここで問題にしているのは、例えば、社長の妻が役員に入っており、妻のタイムカードなどがない際に、「役員である奥さんの勤務実態がわかりませんね。勤務実態を証明できなければ過大役員報酬で否認しますよ」と言われるようなケースです。
このようなケースでは、納税者がいくら役員(妻)の勤務内容や勤務時間を説明しても、それを証明するものがないという理由だけで、調査官は否認しようとしてきますが、これは間違いです。否認したければ、本当にタイムカード等がない以上、別の角度から役員の勤務実態がないことを調査官が証明すべきなのです。
立証責任を押し付けられた場合は、「絶対に」調査官に反論し、立証責任は調査官にあることを主張してください。
その際に、上記国税庁ホームページにある論文を見せることが効果的です。課税庁の人間が書いて自分たちで公表している論文内容を、調査官が個人的な見解で覆すことなどできないのですから。
直近の裁判事例でも
直接的に立証責任について争った事案ではないにしても、平成23年3月25日に出された裁決で、立証責任は基本的に課税庁側にあることを明示しています。
請求人は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した一部の経費について、不動産賃貸業の遂行上直接必要であった部分を明らかにしていないことから、当該経費を必要経費に算入することはできないとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
この裁決では、「請求人(納税者)が、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきと主張する経費について、必要経費についての立証責任は、原則として原処分庁にあるとした」旨を明示しています。
立証責任が課税庁にあるという「事実」は、国税庁のホームページにだけ公式見解があるのはなく、さまざまな判決・裁決で明示されていることであって、これはすでに覆すことができない見解なのです。
申告納税制度における立証責任について
こちらのページをご参考ください。
まとめますと下記となります。
・申告納税制度においては納税者が自ら提出した申告書はまず尊重されるため優位性を有している。
・反対に無申告者等は当該優位性を放棄している。
・更正の請求、後出し簿外経費は納税者が立証責任を負うと言える。
税務調査における立証責任について
こちらのページをご参考ください。
まとめますと下記となります。
・税務調査の延長に税務訴訟が存在するため税務調査において立証責任を考えることは有意義である。
・税務調査における立証責任は国税にあるといえるが、納税者に有利な項目については納税者に立証責任があると言える。
重加算税賦課要件事実の立証責任について
こちらのページをご参考ください。
まとめますと下記となります。
・重加算税賦課要件事実の立証責任は国税にあるといえます。
・過少申告加算税の免除規定である正当な理由、更正があるべきことを予知していたかどうか、の立証責任は納税者にあります。
後出し簿外経費における立証責任について
こちらのページをご参考ください。
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
まとめますと下記となります。
・これまで後出し簿外経費については納税者が立証責任を負うとされるはずが、国税が負っていたような現状がありました。
・これを防ぐために後出し簿外経費については納税者が立証責任を負うことが明文化されたと言えます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します