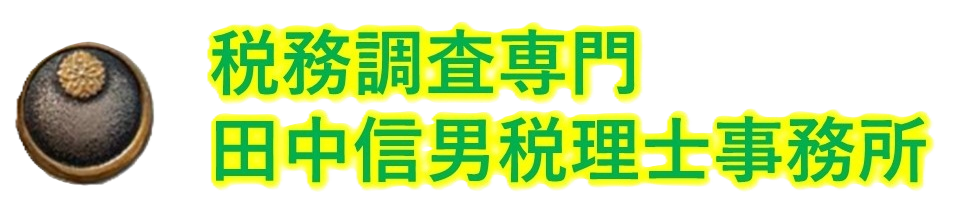現在は無予告調査が明文化されていることについて
(2026年2月10日更新)
結論
・平成25年(2013年)1月1日以降は大改正により税務調査のルールが明確化されており理不尽な税務調査は減少傾向にあると考えます。
・驚くべきことですが、実は平成24年以前は無予告調査について明文化されていませんでしたが、平成25年以降は無予告調査について明文化されております。
・これにより、税務署職員の勝手な判断により、無予告調査は実施できなくなっております。
・これが平成25年以降は理不尽な税務調査は減少していると思われる理由の一つです。
・無予告調査が来た場合であっても調査開始を待ってもらい税理士を探すことが望まれます。
以下で詳細を記述します。
かつては不透明であった税務調査のルールですが、平成25年(2013年)1月1日以降は整備化されて、昔より理不尽な税務調査は減少傾向にある、というのが弊所の見解です
平成23年(2011年)度改正で、平成25年(2013年)1月1日以後に開始する税務調査から、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続等を法律上明確化するなどされました、代表的な7項目です。
1.事前通知の原則化及び明確化(事前通知をしない場合の例示)
2.帳簿書類等の預かりに対する預り証発行及び署名押印
3.調査結果の説明と修正申告等の勧奨(教示文に署名押印)
4.更正等は5年が基準に
5.不利益処分などを行う際の処分理由の記載
6.更正等をすべきと認められない場合の通知の明確化
7.再調査の明確化
今回は、事前通知の原則化及び明確化(事前通知をしない場合の例示)、を見ていきます。
無予告調査とは
税務調査は2種類あります。事前に調査にいくと予告されるもの、事前に連絡のない無予告調査です。当該無予告調査ですが、平成24年(2012年)以前は法的な要件はありませんでした。しかし、平成23年(2011年)度改正で、平成25年(2013年)1月1日以後に開始する税務調査からの無予告調査は法定化されることになりました。
根拠規定を見ると、国税通則法第74条の9の規定は(原則として)実地の調査を行う場合は事前通知をしなければならないと定義しています。一方で国税通則法第74条の10は事前通知を要しない場合として無予告調査について規定しています。
国税通則法第74条の10は前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又は「その営む事業内容に関する情報」その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、「違法又は不当な行為を容易にし」、「正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。(「」は弊所が加筆)
ここで以下を読み取ることができます。事前通知を要しない要件として
①違法又は不当な行為を容易にすると認める場合
②正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがあると認める場合
③その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合
しかし①~③については具体性に欠けると考えられます。そのため通達において更なる解説が存在します。
・法令解釈通達、第4章、法第74条の9~法第74条の11関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)、第2節事前通知に関する事項、における5-7、5-9、5-10において解説が存在します。
まず国税庁は前提条件のようなものを明言しています。
「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しないとは判断しない」と明言しております。
(「その営む事業内容に関する情報」の範囲等)
5-7 法第74条の10に規定する「その営む事業内容に関する情報」には、事業の規模又は取引内容若しくは決済手段などの具体的な営業形態も含まれるが、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する。
(「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示)
5-9 法第74条の10に規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合とは、例えば、次の(1)から(5)までに掲げるような場合をいう。
(1)事前通知をすることにより、納税義務者において、法第128条第2号又は同条第3号に掲げる行為(不提示・虚偽答弁・忌避妨害等)を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
(2)事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
(3)事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
(4)事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合
(5)事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、上記(1)から(4)までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。
(「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合の例示)
5-10 法第74条の10に規定する「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合とは、例えば、次の(1)から(3)までに掲げるような場合をいう。
(1)事前通知をすることにより、税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合。
(2) 事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、又は応答がなかった場合。
(3) 事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難な場合
弊所が理解しやすいよう簡易的に改めてまとめます。
①事前通知をすることにより妨害等を行うことを助長することが合理的に推認される場合
②事前通知をすることにより逃亡することが合理的に推認される場合
③事前通知をすることにより調査に必要な帳簿書類を偽造することが合理的に推認される場合
④事前通知をすることにより過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合
⑤事前通知することにより納税者の関係者と共謀して調査への協力を控えるよう要請することが合理的に推認される場合
⑥事前通知をすることにより税務代理人以外の第三者が調査立会いを求め、それにより調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合
⑦電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、又は応答がなかった場合
⑧事前通知先が判明しない等、事前通知を行うことが困難な場合
さらに簡易的にまとめると以下となります。
・事前通知をすることにより納税者が、妨害する、逃亡する、帳簿を改ざんする、帳簿を適正に見せかける、関係者と共謀する、第三者の立会を求めて支障を及ぼす、ことが合理的に推認される場合
・事前通知の連絡そのものが困難な場合
ここで「合理的に推認」にも着目します。
国税の一方的な合理的推認により判断されます
ここで「合理的に推認される場合」の基準について気になります。ここで国税庁は、「事前通知を行わないこととした理由を説明しない」と明言しています。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
問21 事前通知無しに実地の調査が行われた場合、事前通知が行われなかった理由の説明はありますか。また、事前通知をしないことに納得できない場合には不服を申し立てられますか。
法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていません。(省略)また、事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、事前通知が行われなかったことについて納得いただけない場合でも、不服申立てを行うことはできません。
無予告調査でも調査日程の変更は可能と解されます
無予告調査でも調査日程の変更は可能かどうかについては以下を研究しました。
・ネット検索
・書籍
ネット検索の結果
ネット検索においては、無予告調査でも調査日程の変更は可能という記述が多数存在しました。
書籍の研究結果
現在研究中です。
以上より無予告調査でも調査日程の変更は可能と結論付けました。
無予告調査の調査に来たが調査日の日程を交渉し、改めて調査の初日を決定し、その改めた調査日初日の前日までに提出した申告書は税務調査開始前の取り扱い、更正の予知無しの取り扱いとなり罰則の回避できるのか?
掲題についての弊所の見解は以下となります。
・明確な根拠は現在不明ですが恐らく、税務調査開始前の取り扱い、更正の予知無しの取り扱い、と解されます。
・また仮に上記の取り扱いでは無かったとしても、納税者に残された最後の手段はこれしかないため、これに挑戦するしかない、と解されます。
もし仮に「税務調査開始前の取り扱いであった場合に回避可能な罰則」は下記となります。
売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
理由は以下となります。
売上帳簿無し加算税加重は「税務調査中に指摘」が要件となるためです。
後出し簿外経費不可も「税務調査中に指摘」が要件となるためです。
もし仮に「更正の予知無しの取り扱いであった場合に回避可能な罰則」は以下となります。
国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています
高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
理由は以下となります。
・重加算税賦課は更正の予知があった場合が要件となるためです。
・高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げも更正の予知があった場合に加重されるためです。
まとめ
・現在は、原則が予告調査、例外として無予告調査となります。
・無予告調査も調査日の変更は可能と解されます。
・無予告調査は突然やってくるため冷静な対処は難しいかもしれませんが、突然やってきた調査官に対してはこれから税理士を探すなどの理由で一旦調査を待ってもらい、税理士へ連絡することが望ましいと考えます。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します