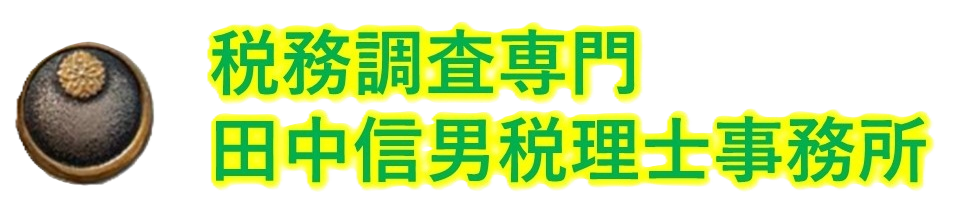税法における更正という文言を正しく理解しましょう
(2026年1月22日更新)
結論
・税法の更正は、更生ではなく更正です。
・更正の請求をするための更正の請求書や添付書類や手続きは他の申告と異なります。
・更正の請求の立証責任は納税者が負っていると解されます。
・隠蔽仮装行為に基づく更正の請求も重加算税賦課の対象となりました。
以下で詳細を記述します。
まず、更生ではなく更正です
ネット記事等で、更正とすべきところを更生と誤変換の誤字で記述している場面が散見されます。これはパソコン等の変換がまず更生がでてきることに起因していると解されます。
更生:生き返ること、よみがえること、精神的、社会的に、また物質的に立ち直ること、となります。
また更正の予知、更正の予知なし、という言葉も存在します。これを、更生の余地、としてしまうと、
更生の余地がない:改善や立ち直る見込みがない状態
となり、語感はそっくりだが全く意味は違うこととなりますので、ご注意ください。
税法における更正とは
まず前提としては、税務申告書の内容が誤っていた場合となります。
この場合において納税者が税務署に対し申告内容を正す手続きが、訂正申告、修正申告、更正の請求となります。
これに対して税務署側が納税者に対して行う手続きが、更正または決定になります。
なお更正と決定の違いに触れておきますと、更正とは「期限内」の申告に対して税額を正す処分であり、税額が増える場合も減る場合も、いずれも「更正」となります。税額が増えるものを「増額更正」、減るものを「減額更正」といいます。(税務調査においては追徴が目的であるため基本的に「増額更正」であると考えられます。)これに対して決定は、「期限後」の申告の税額を正したり、無申告の相手に税金を課したりする処分です。
・期限内申告に対する税務署からの指摘=更正
・期限後申告又は無申告者に対する税務署からの指摘=決定
更正の請求は納税者が税務署へ減額更正してくださいと請求することと言い換えることができるかもしれません
更正の請求の定義は下記となります。
「更正の請求」とは,納税義務者が申告した税額が計算誤り等により過大であることを知った場合に,納税義務者が自ら申告内容の是正(税額の減額)を課税庁に請求できる権利です。
(京都市情報館ホームページより)
更正の請求の仕組み
提出する申告書からみる更正の請求の特殊性
まず下記の違いについてご理解お願いいたします。
・期限内申告において計算した結果税金還付となった場合=通常の申告書の税額欄に△(さんかく)又は―(マイナス)を記述すれば提出及び還付を受けることが可能
・期限後において税金計算の修正により税金還付が算出された場合=修正申告書の税額欄に△(さんかく)又は―(マイナス)を記述しても提出不可=更正の請求書で提出しなければならない=税務ソフトにおける修正申告書作成機能を利用して更正の請求を試みることは誤っております
添付資料等からみる更正の請求の特殊性
・更正の請求の根拠となった資料の添付が必要となります。
・税務署から添付した資料に加え、追加資料を求めてくる場合もあります。
・更正の請求が認められず、更正の請求に対してその請求をすべき理由がない旨の通知書、が通知される場合もあります。
・つまり更正の請求については納税者に立証責任があると解されます。立証責任についてはこちらのページをご参考ください。
更正の請求と重加算税
・令和6年度(2024年度)改正により隠蔽・仮装したところに基づき「更正請求書」を提出した場合を重加算税の賦課対象に加えることとなりました。
・令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用であるため、個人事業主については令和6年度(2024年度)申告からとなります。法人については12月末が休日扱いになるため、1月最初の税務署営業日が申告期限となる令和6年(2024年)10月決算法人から対象となります。
・改正の経緯としては、申告後に隠蔽・仮装したところに基づき「更正請求書」を提出した場合であったとしても、重加算税を賦課することができない制度が問題視されていたためとなります。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します