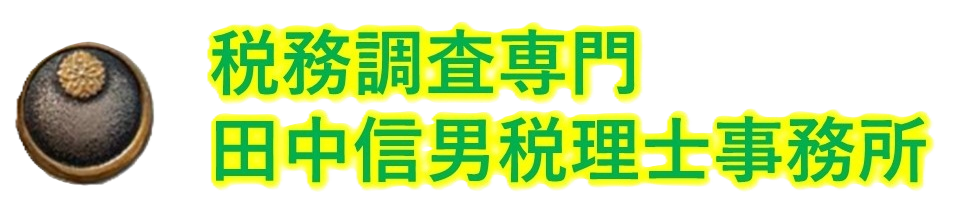隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
(2026年1月21日更新)
結論
・事前自主修正期限後申告をせずに隠蔽仮装又は無申告状態のまま税務調査を受けた納税者は、原則的に間接経費の計上が認められず、例外的に証拠能力の高い資料を提示して認められた場合にのみ間接経費の計上が認められるという通常では考えられない不利な状況となることが明文化されました。これが後出し簿外経費不可と呼ばれています。
・学説等によれば後出し簿外経費については納税者側に立証責任があるとされていたものの、実務では税務署が税務調査において大量に提出された後出し経費を精査するという理不尽を税務署が負っていたようです。
・R5年(2023年)分以後については、事前自主修正期限後申告をせずに隠蔽仮装又は無申告状態のまま税務調査を受けた納税者の経費主張はまず拒否されることとなります。
・当該規定に該当する場合は隠蔽仮装行為に関わる経費だけでなくそのた申告済みの経費についても適用があり、原則的に疑われることとなります。
・反対を言えば、事前自主修正期限後申告をすれば当該規定の適用はない、となります。
・適用時期は、個人事業主については令和5年(2023年)分以後の所得税について適用され、法人については令和5年(2023年)1月1日以後開始する事業年度について適用されます。
以下で詳細を記述します。
後出し簿外経費不可とは
後出し簿外経費不可という文言は正式な用語ではないと思われます。
・国税庁ホームページの法人税法において「証拠書類のない簿外経費についての損金不算入措置」という文言は見つけることができました。(国税庁ホームページ:令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明)
・国税庁のホームページの所得税法においては「証拠書類のない簿外経費についての必要経費不算入措置」という文言は見つけることはできませんでした。(2025年8月8日現在)
・財務省トップページ 税制 毎年度の税制改正 税制改正の概要 令和4年度 令和4年度 税制改正の解説 所得税法等の改正 詳解、において「証拠書類のない簿外経費」という文言が見受けられました(財務省トップページ 税制 毎年度の税制改正 税制改正の概要 令和4年度 令和4年度 税制改正の解説 所得税法等の改正 詳解)
・財務省トップページ 税制 毎年度の税制改正 税制改正の概要 令和4年度 令和4年度 税制改正の解説 法人税法等の改正 詳解、において「証拠書類のない簿外経費」という文言が見受けられました(財務省トップページ 税制 毎年度の税制改正 税制改正の概要 令和4年度 令和4年度 税制改正の解説 法人税法等の改正 詳解)
以上を総合勘案すると、
証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置の規定について、誰かが「後出し経費不可」と言い出し、それが広まったのではないか
と推測されます。
以下においては、証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置、後出し経費不可、の文言のいずれも使用いたします。
財務省資料において当該改正の正式名称が記述されてます
・令和4年度 税制改正の解説 所得税法等の改正 詳解においては、「五 家事関連費等の必要経費不算入等の改正」とあります。
・令和4年度 税制改正の解説 法人税法等の改正 詳解においては、「二 不正行為等に係る費用等の損金不算入制度の改正」とあります。
根拠規定
根拠規定:法人税法55条3項
3 内国法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について国税通則法第25条(決定)の規定による決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の第22条第3項第1号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。)、同項第2号に掲げる費用の額及び同項第3号に掲げる損失の額(その内国法人が当該事業年度の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第74条第1項第1号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る法人税についての調査があつたことにより当該法人税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した同法第19条第4項第1号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該原価の額、費用の額又は損失の額については、この限りでない。
一 次に掲げるものにより当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその内国法人において証明した場合を含む。)
イ その内国法人が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)又は第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
ロ イに掲げるもののほか、その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該原価の額、費用の額又は損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
根拠規定:所得税法45条3項
3 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかつた場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として政令で定める額を除く。以下この項において「売上原価の額」という。)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(その居住者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、これらの額のうち、その提出した当該確定申告書に記載した第120条第1項第1号(確定所得申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る修正申告書(その申告に係る所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知した後に提出された修正申告書を除く。)に記載した国税通則法第19条第4項第1号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額を除く。)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。
一 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合(災害その他やむを得ない事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができなかつたことをその居住者において証明した場合を含む。)
イ その居住者が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)又は第232条第1項若しくは第2項(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定めるところにより保存する帳簿書類
ロ イに掲げるもののほか、その居住者がその住所地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
二 前号イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合(同号に掲げる場合を除く。)であつて、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
適用時期
・個人事業主については令和5年(2023年)分以後の所得税について適用されます。
・法人については令和5年(2023年)1月1日以後開始する事業年度について適用されます。
財務省の解説
令和4年度 税制改正の解説 所得税法等の改正 詳解p82-83より
・所得課税においては、裁判例によって示されているように「所得金額」や「必要経費の存否及び額」については、原則として課税当局の側に立証責任があるとしつつ、「簿外経費」については、納税者側に立証責任があると解する場合が多いとされています。しかしながら、実際の事案として、所得税の税務調査において家事関連費の計上を発見した後に、納税者が簿外経費の存在を後から主張し、課税当局が多大な事務量を投入してその簿外経費が全て存在しないことを立証して更正に至ったという悪質な事案があります。
・これを踏まえ、納税者が事実の仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、課税当局による反面調査等によってもその簿外経費の基因となる取引が行われたと認められない場合には、その簿外経費は必要経費に算入しないこととする措置を講ずることとされました。
・ また、(期限内申告済みの)場合であっても、隠蔽仮装行為に関連する額のみが本措置による必要経費不算入の対象となるのではなく、隠蔽仮装行為に関連しないものも含めてその年分の全て(直接費用、販売費、一般管理費等)の額が本措置による必要経費不算入の対象となります。
財務省の解説のさらに要点解説
・R5年(2023年)分より前であっても、簿外経費については納税者に立証責任があるはずであった。しかし実務上は、税務調査において納税者が後出しで証拠能力の薄い、根拠の乏しい経費を主張してきた場合でも税務署は拒否できずに精査する時間コストを強いられてきた。
・R5年(2023年)分以後においては、隠蔽仮装納税者や無申告納税者といった不誠実な納税者に対しては簿外経費を税務署が拒否できる法整備がされた。
・当該規定は、隠蔽仮装に関連しない経費にも影響を及ぼす規定である。
根拠規定の要約解説
根拠規定を要約します。
・対象者は事前自主修正期限後申告せずに税務調査を受けた個人事業主及び法人は、原則として経費計上が認められません。
・しかし、(原則として経費を認めないことは厳しすぎるため)仕入経費に関する帳簿資料が存在する場合には計上を認めますが、後からとってつけたような手書きの伝票による経費は基本的には認めないし、当該経費計上の可否判定のための反面調査の手間コストはかけない、と税務署が主張できるようになった。
税法における立証責任について
立証責任についてはこちらのページをご参考ください。
まとめますと、申告納税方式においては、納税者が期限内申告をしていれば原則的にまずは全面的に納税者の申告内容が尊重されます。しかし意図的な過少申告者や無申告者はその信頼を除去される、ということになります。
代表的な事例を想定:相手方からの請求書や領収書が存在しないが確かに存在した外注費を納税者自らが作成した手書きの伝票で外注費の存在を主張する、場合など
〇事例1:ある売上を除外していたが、それに伴う外注費が存在しているが当該外注費の証拠能力が乏しい過少申告者Aに調査通知があった場合
・税務調査前に事前自主修正申告せずに調査を受けると、売上除外は売上計上を認定されるが、外注費は否認される、という可能性が高まります。
・税務調査前に事前自主修正申告すれば、売上計上と共に証拠能力が乏しい外注費の存在についてもまずは尊重されることになります。
〇事例2:帳簿資料がほとんど残っていない無申告者Bに調査通知があった場合
・税務調査前に事前自主期限後申告せずに調査を受けると、売上経費ともに税務調査官主導で決定していき、納税者の意見は尊重されなくなります。
・税務調査前に、記憶やメールやメモ帳や手帳から推測される売上や経費により金額を算出し、事前自主期限後申告すれば、当該申告書はまずは尊重されることになります。
証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置改正の経緯
証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置の改正の経緯としては、
・隠蔽仮装をしていた納税者の簿外経費の主張として事後的に提出された書類の確認に多大な事務量を要した事例
・無記帳・無申告の者に対する推計課税事案
のような事例が、かつてより問題視されていたためです
簿外経費の主張として事後的に提出された書類の確認に多大な事務量を要した事例(第6回 納税環境整備に関する専門家会合(2021年8月10日)資料一覧)
【事案の概要】
●調査対象者は翻訳業務を行う個人事業者。調査の過程で、多額の家事関連費(自宅や親族宅の家賃、飲食代、衣料品代等が数億円)が費用計上されていることを把握。
●上記問題点を指摘したところ、計上漏れ経費がある旨の申立てがあった。後日、家事関連費とほぼ同額の外注費として1,000枚超の領収書(支払先数百名分)が提出され、全て現金手渡しでの支払いであったと主張。領収書記載の外注先は、大半が海外居住者であり、国内居住者の大部分についても居住実態が確認できない者だった。
●調査官は、上記領収書の解明及び居住等調査に加え、反面調査等により事実関係を確認した結果、領収書記載の取引が虚偽であると認定。必要経費として認容しないこととして更正処分を行ったが、上記の調査に当たっては約1,000人日の事務量を投下。
【問題点】
●後出し的な簿外経費の主張であっても、当局側が多大な事務量を投下してその真偽を確認しなければならない。特に現金払いの簿外経費については、銀行取引明細等による確認ができないため、支払の事実を確認する負担が大幅に増加する。
連年事業を行うも無記帳・無申告の者に対する推計課税事案(第6回 納税環境整備に関する専門家会合(2021年8月10日)資料一覧)
【事案の概要】
●調査対象者は防水工事を営む個人事業者。明らかに事業を営んでいるが連年無申告。
●再三にわたって連絡票を差し置いたにもかかわらず、納税者から一切連絡がなかったため、近隣の銀行や取引先に対する反面調査を実施。
●反面調査により把握した売上金額(実額)と、同業者の経費率から算出した必要経費を用いて所得金額を推計し、決定処分を行った。【調査期間:6ヵ月、重加算税の賦課なし。】
【問題点】
●「無記帳の者」、「帳簿書類の保存(提示)をしない者」であっても、推計課税により、同業者と同程度の必要経費が認められる。
● 一般の事業者が果たしている、「記帳」や「帳簿書類の保存(提示)」の義務を果たさなくても「仮装隠蔽」には当たらないことから、重加算税(ペナルティ)を受けない。
影響大と推測される業種(弊所独自の推測)
・資産を仕入て販売譲渡を行う、卸売業、小売業、製造業を除くサービス業が全般的に影響が大きいと推測されます。
・外注費が多額と見込まれる、建設業や一人親方の大工などが全般的に影響が大きいと推測されます。
・ユーチューバーは、直接経費が少ないので影響が大きいと推測されます。
その他気が付いた時点で加筆します。
影響大と推測される業種(事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を参考に)
・経営コンサルタント←直接仕入経費が少ないサービス業と解されます。
・タイル工事←外注費が高額と解されます。
・冷暖房設備工事←外注費が高額と解されます。
・バー←ヘルプホスト、ヘルプホステスなどの外注費が高額と解されます。
・電気通信工事←外注費が高額と解されます。
・システムエンジニア ←直接仕入経費が少なく、外注費が高額と解されます。
・商工業デザイナー←直接仕入経費が少なく、外注費が高額と解されます。
・不動産代理仲介←直接仕入経費が少ないサービス業と解されます。
・外構工事←外注費が高額と解されます。
・型枠工事←外注費が高額と解されます。
・一般貨物自動車運送←直接仕入経費が少ないと解されます。
影響大と推測される業種(法人税、不正発見割合の高い10業種を参考に)
・土木工事←外注費が高額と解されます。
・職別土木建築工事←外注費が高額と解されます。
・一般土木建築工事←外注費が高額と解されます。
・管工事←外注費が高額と解されます。
・その他の道路貨物輸送←直接仕入経費が少ないと解されます。
・バー・クラブ ←ヘルプホスト、ヘルプホステスなどの外注費が高額と解されます
影響大と推測される業種(法人税、不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種を参考に)
・運輸附帯サービス←直接仕入経費が少ないと解されます。
・その他の対事業所サービス←直接仕入経費が少ないサービス業と解されます。
・その他の不動産←直接仕入経費が少ないサービス業と解されます。
・情報サービス、興信所←直接仕入経費が少ないサービス業と解されます。
当該規定を回避するための策
事前自主修正期限後申告をすれば当該規定の適用はない、となります。
まとめ
・隠ぺい仮装を行った者は、重加算税が賦課されることに加えて、後出し簿外経費も認められなくなりました。
・無申告者が重加算税が課税されにくいことに対する批判の影響もあり、無申告者に対する厳罰化として後出し簿外経費が認められなくなりました。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します