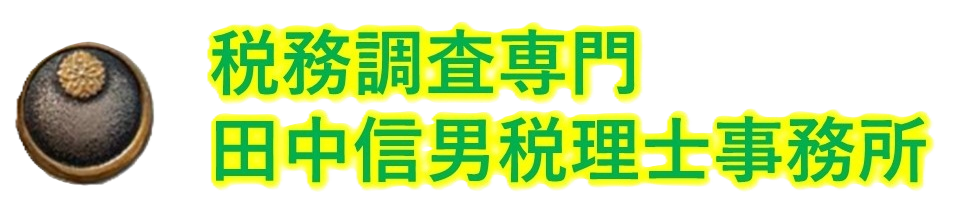売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
(2026年1月21日更新)
結論
・令和4年(2022年)度税制改正により、税務調査における売上帳簿に関する指摘で、帳簿の存在の有無や申告漏れ金額差に応じて無申告加算税又は過少申告加算税が5~10%加重される規定が定められました。
・本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。
・本改正は、無記帳無保存無申告者に対して開き直りによる重加算税回避の逃げ道を加重によって封鎖する目的と解されます。
・本改正は、売上過少申告者に対してうっかりミスと言い逃れによる重加算税回避の逃げ道を加重によって封鎖する目的と解されます。
・近年における改正による罰則は国が事前自主修正無申告解消を暗に推奨しているメッセージであると弊所は独自に分析しております。
以下で詳細を記述します。
令和4年(2022年)度税制改正により、税務調査における売上帳簿に関する指摘で、帳簿の存在の有無や申告漏れ金額差に応じて無申告加算税又は過少申告加算税が5~10%加重される規定が定められました
本改正の内容を分析します。
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月国税庁)P1より
記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下①〜③において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が10%又は5%加重されることとなりました。
① 帳簿の提示等をしなかった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
② 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満
だった場合
⇒ 過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
③ 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満
だった場合(②に該当する場合を除きます。)
⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。
ここで要件を簡潔にまとめます。
税務調査において、売上帳簿を提示しなかった場合、売上帳簿へ本来記載すべき金額の1/2未満しか記載がなかった場合、2/3未満しか記載がなかった場合、それぞれにおいて無申告加算税の加重、過少申告加算税の加重が適用されます。
ここで改めて「帳簿」の定義について、国税庁は以下のように記述しています。
帳簿=仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
こちらのページで解説しておりますが、「帳簿」は申告書に添付して税務署に提出するケースは基本的に無く、基本的には手元に作成しておき、税務調査において提示するものとなります。
国税庁Q&Aの具体例を分析します。
したがって、例えば、個人事業者に対する税務調査において提示等がされた帳簿について、本来記載等をすべき売上⾦額が2,000万円であったにもかかわらず、実際には800万円しか記載等がされておらず、その結果、申告漏れが生じていた場合には、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合に該当することから、申告漏れとなっていた1,200万円に対して新たに納める必要のある所得税額を基礎として課される過少申告加算税の割合が10%加重されることとなります。
(注) 申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の本税の割合が加重されるものではありません。
上記の例は、当初申告において売上800万円と記載した過少申告者が税務調査を受けた結果、売上漏れを指摘されて年商2,000万円と認定された場合に、納税者が800万円と集計した売上帳簿を提示したために過少申告加算税が10%加重されたことを想定した具体例と解されます。
では上記例を参考に、無記帳無保存無申告者と仮定した場合の事例に変換して記述いたします。
したがって、例えば、個人事業者に対する税務調査において提示等がされた帳簿について、本来記載等をすべき売上⾦額が2,000万円であったにもかかわらず、実際には0円しか記載等がされておらず(帳簿を提示せず)、その結果、申告漏れ(無申告)が生じていた場合には、帳簿の提示等しなかった場合に該当することから、申告漏れとなっていた2,000万円に対して新たに納める必要のある所得税額を基礎として課される無申告加算税の割合が10%加重されることとなります。
(注) 申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の本税の割合が加重されるものではありません。
上記の例は、当初申告において無申告者であった者が税務調査を受けた結果、売上漏れを指摘されて年商2,000万円と認定された場合に、納税者が売上帳簿を提示しなかったために無申告加算税が10%加重されたことを想定した具体例と解されます。
そうするとここで下記の疑問が生じます。
・本来記載等をすべき売上⾦額が2,000万円であり、売上帳簿等においても2,000万円と記述していたが、申告書に800万円と転記していた場合はどうなるか。
・本来記載等をすべき売上⾦額が2,000万円であり、売上帳簿等においても2,000万円と記述していたが、無申告であった場合はどうなるか。
これらについては後述します。
本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます
適用時期の詳細については以下となります。
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月国税庁)P2より
したがって、各税目においては、通常、それぞれ以下のとおり適⽤される場面が生じ得ることとなります。
・ 申告所得税・・・令和5年分から適⽤。
・ 法人税・地⽅法人税・・・令和5年10月決算期分(令和5年12月31日は税務署が休業日であるため法定提出期限が令和6年1月となるため)から適⽤。
・ 消費税・・・課税期間が1年間の場合には、申告所得税、法人税・地⽅法人税と同様。
弊所独自の分析ですが、本措置の目的は調査開始後における売上漏れに対する納税者の重加算税回避のための言い訳の逃げ道を加算税加重という方向性で逃げ道を封鎖する又墓穴を掘らす目的と解しております
掲題についての説明ですが、下記の表をご覧ください。
(表1)売上帳簿不十分改正による影響予想表20250812
上記表を文章化すると以下となります。
・無申告者が事前無申告解消せず、売上帳簿も作成せず税務調査を受けた場合(現状よくあるケース)
・無申告者が事前無申告解消せず、本措置適用を回避するため売上帳簿も作成し税務調査を受けた場合(あまり考えにくいレアなケース)
・無申告者が事前無申告解消する場合(弊所推奨のケース)
・過少申告者が事前自主修正申告せず、売上帳簿も修正せず税務調査を受けた場合(現状よくあるケース)
・過少申告者が事前自主修正申告せず、本措置適用を回避するため売上帳簿を修正して税務調査を受けた場合(あまり考えにくいレアなケース)
・過少申告者が事前自主修正申告する場合(弊所推奨のケース)
順番に検証します。
●無申告者が事前無申告解消せず、売上帳簿も作成せず税務調査を受けた場合(現状よくあるケース)
・予想される納税者の主張は、売上帳簿も何も無いから申告しなかった無申告は認めますが、隠蔽仮装の重加算税賦課は認めません。
・税務署調査官は、無申告加算税賦課は諦めたとしても、本措置による加重を主張すると解されます。
●無申告者が事前無申告解消せず、本措置適用を回避するため売上帳簿も作成し税務調査を受けた場合(あまり考えにくいレアなケース)
・本件措置を回避するには正確な売上帳簿を作成すれば良いというところに目をつけ、正確な売上帳簿を作成するが事前無申告解消はしなかった、と納税者は主張すると考えます。
・税務署調査官は、売上帳簿により売上を認識していたにも関わらずあえて申告しなかったとして無申告重加算税を主張すると解されます。
●無申告者が事前無申告解消する場合(弊所推奨のケース)
・近年の罰則化を考えると、事前無申告解消が最善策であると弊所は考えます。
●過少申告者が事前自主修正申告せず、売上帳簿も修正せず税務調査を受けた場合(現状よくあるケース)
・予想される納税者の主張は、うっかりミスと主張すると解されます。
・税務署調査官は、まずうっかりミスを否定し重加算税賦課を主張しますが、重加算税賦課は諦めたとしても、本措置による加重を主張すると解されます。
●過少申告者が事前自主修正申告せず、本措置適用を回避するため売上帳簿を修正して税務調査を受けた場合(あまり考えにくいレアなケース)
・本件措置を回避するには正確な売上帳簿を作成すれば良いというところに目をつけ、正確な売上帳簿に修正するが事前修正申告はしなかった、と納税者は主張すると考えます。
・税務署調査官は、売上帳簿により正確な売上を認識していたにも関わらず過少申告したとして、重加算税を主張すると解されます。
●過少申告者が事前自主修正申告する場合(弊所推奨のケース)
・近年の罰則化を考えると、事前無申告解消が最善策であると弊所は考えます。
まとめ
近年における改正による罰則は国が事前自主修正無申告解消を暗に推奨しているメッセージであると弊所は独自に分析しております。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します