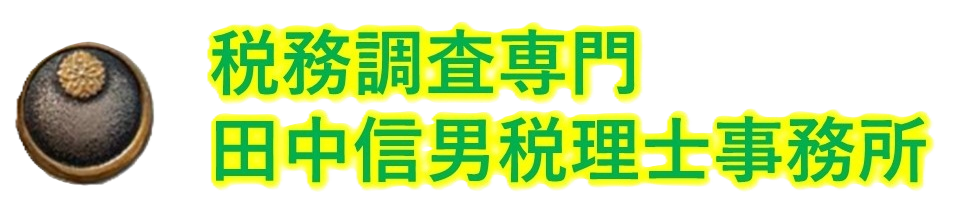レシート領収書保存が少ない無申告者の調査通知後の事前自主申告は不利であるからすべきではないは本当かについて弊所の考え
(2026年1月21日更新)
結論
・ネット検索で散見される「レシート領収書保存が少ない無申告者の調査通知後の事前自主申告は不利であるからすべきではない、税務調査開始後において調査官と交渉して費用を計上するべきだ」という意見に対して弊所は否定的な見解です。
・レシート領収書保存が少ない無申告者もいくつかパターンがあり、あるパターンに該当する場合は意図的無申告重加算税の可能性もあると考えられます。
・近年は無申告の状態のまま税務調査を受けることに対する罰則化の改正が進んでおり、弊所はこれは税務調査前無申告解消をすべきという国からのメッセージであるととらえております。
・究極的にはすべて概算で事前自主期限後申告も可能という書籍の記述もあり、弊所も最終手段として同意します。
以下で詳細を記述します。
ネット検索で散見される「レシート領収書保存が少ない無申告者の調査通知後の事前自主申告は不利であるからすべきではない、税務調査開始後において調査官と交渉して費用を計上するべきだ」という意見に対して弊所は否定的な見解です
掲題の通りですが、上記の論者の論拠は以下となります。
・レシート領収書が少ない場合は売上に対する仕入経費を相殺して削ることができず、所得が大きくなる傾向があるのですべきではない。
・税務調査開始後において調査官に対して交渉で、推計してもらうなどして計上すべき。
という内容です。弊所は以下の観点から上記の主張に否定的です。
・無申告者のうちには意図的無申告重加算税と認定される可能性が高い無申告者も含まれていること
・意図的無申告ではない単純無申告で無申告重加算税を賦課しにくい無申告者に対しては無申告加算税加重の罰則化が強まっていること
以下で説明します。
レシート領収書保存が少ない無申告者もいくつかパターンがあり、あるパターンに該当する場合は意図的無申告重加算税の可能性もあると考えられます
無申告者には下記のパターンがあると解されます。
●現金取引のみで売上資料及び仕入経費資料の両方が無記帳無保存単純無申告者
●売上資料は無保存であるが売上金は通帳入金で管理していたため再発行復元可能及び仕入経費資料は無保存の無申告者
●まず、現金取引のみで売上資料及び仕入経費資料の両方が無記帳無保存単純無申告者については以下の見解です。
・資料が無かったから申告できなかったという開き直りの発言で、無申告重加算税の賦課は回避出来るかもしれません。
●一方で、売上資料は無保存であるが売上金は通帳入金で管理していたため再発行復元可能及び仕入経費資料は現金取引のみで無保存の無申告者については以下の見解です。
・大切な通帳を紛失するとは考えにくいとして紛失したという言い分が認められず、さらに売上金の認識はなかったという言い分も認められず、意図的な破棄、隠蔽、として無申告重加算税の対象となる可能性があります。
こちらのページをご参考ください。
無申告に対して重加算税が賦課され調査期間は最大7年間となるかどうかについて
このようなケースであっても無申告状態のまま税務調査に臨むことは適切なのでしょうか、弊所は同意できません。
近年は無申告の状態のまま税務調査を受けることに対する罰則化の改正が進んでおり、弊所はこれは税務調査前無申告解消をすべきという国からのメッセージであるととらえております
掲題についてまとめます。調査通知後から税務調査開始前までに事前自主修正申告で回避できる罰則については以下となります。
売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
上記の罰則については、税務調査前までに隠蔽仮装、無申告の解消をしなければ適用される可能性がある近年の改正となります。
またそもそも、申告納税制度においては、納税者の自主的な申告により国、国税、税務署は後手に回る構図となります。
税務調査を理解するために申告納税制度を理解しよう
税法における立証責任について
このようなケースであっても無申告状態のまま税務調査に臨むことは適切なのでしょうか、弊所は同意できません。
究極的にはすべて概算で事前自主期限後申告も可能という書籍の記述もあり、弊所も最終手段として同意します。
前提の注意点としては、資料が全くないという意味が現状資料が全くなくて再発行可能性がないという意味であり、現状は資料が無いが再発行は可能となる場合、税務署が資料を権限で収集して実額算定される恐れ及び再発行できるのにせず紛失ではなく意図的に破棄したとされる可能性が高いからとなります。
・大村大次郎「フリーランス&個人事業主でお金を残す!元国税調査官のウラ技第4版」㈱技術評論社(2017年10月21日)p162-165より
概算で申告するというウラ技
領収書などをまったく残していない場合の奥の手とは?
無申告だけは避けないといけない
先ほど、領収書がなくても経費がなくても経費にする方法を紹介しました。それは万が一、領収書のもらい忘れや紛失があったときの対処方法で、あくまで領収書を集めるのが基本です。しかしながら、中にはほとんど領収書を残していない、というような方もいるかもしれません。
白色申告でも、「必要な帳票類は残さなければならない」と、税法で記帳義務が課されるようになりました。それをおそれて申告しないなどとなると、個人事業主、フリーランサーは大変なことになってしまいます。
筆者の知り合いにも、そういう人がいました。その人は、もう何年も確定申告をしませんでした。確定申告をしたいのだけれど、領収書やレシートを残していない、だからしたくてもできない。1年しないと2年しなくなり、ついには5~6年ずっと確定申告をしていない状態でした。この状態では、従業員用がいても、従業員を社会保険に加入させることが難しくなり、所得証明書なども取得できないので、社会的な信用も失われてしまいます。そういった事態を避けるために、領収書がまったくなくてもできる緊急避難的な確定申告方法を紹介しましょう。
手がかりを見つけて数字をはじき出す
簡単に言えば、「概算で申告する」という方法です。「概算」とはいっても、何の根拠もない数字を並べただけでは通用しません。なるべくその概算値に根拠を持たせる必要があります。
たとえば、売上がわからない場合なら、何かを基準にします。「1日の売上」「毎月の売上」「同規模同業者」など、把握できて手がかりになる数字を見つけ出すのです。その数字を基準に年間の売上額をはじき出します。
経費も同じように、根拠になるものを見つけて算出します。水道光熱費だったら、月の平均がどのくらいかからか年額を推し測ります。同じようして、他の経費もはじき出していきます。
税務署も概算で税金を計算することがある
この「概算」は、税務署でやっているのとだいたい同じことです。
税務署の納税相談窓口には、証拠書類や帳簿などまったくない人が申告にやって来ることもあります。税務署としては、なるべく証拠書類を残したり、記帳するように指導していますが、ないものは仕方がないですし、追い返すわけにもいかないので、証拠書類、帳簿などがまったくない状態でも申告を受けるのです。
その場合、毎月のだいたいの売上、経費を聞き取ります。もしわからなければ、「今年は去年と比べてどうでしたか?」と聞き、去年より儲かっていれば去年の申告より少し多めに、去年より悪ければ去年の申告より少し少なめに数字を書く、などというウラ技を使います。もちろん、納税者としては税金はなるべく少ないほうがいいので、だいたい「去年より悪い」というとうなことを言いますが。なぜ税務署員がウラ技を使ってでも申告させるかというと、申告をしないよりは、あいまいであっても申告させたほうがいいからです。
申告をしなければ無申告という扱いになります。そして一度、無申告になった人は、もうなかなか税金の申告をしようとはしません。よって、とりあえず申告だけさせておいて、おいおい指導して、次の年にはきちんとした方法で申告させようというのが税務署の考えなのです。
したがって、領収書がまったくない場合でも、申告をしないよりはしたほうが税務署としてありがたいわけです。領収書も何も残していない場合でも、申告はしたほうがいいのです。
とはいえ、このやり方はもちろん正規の方法ではありません。税金の申告書は、証拠書類を残してそれを元に作成するのがルールです。
よって、概算で申告は税務署から否認されることもあり得ます。なるべく否認されないような方法を紹介していますが、完全でないということをご了承ください。そういうリスクもあることを念頭において、実行するかどうかは自己責任で判断してください。
概算で申告するときの信頼性のある基準とは?
概算で申告する場合、「同業者と比較して」といっても、なかなか同業者の情報はつかめないものです。では、何を基準に申告すればいいのか。記録がないのだから、何を基準にするにしろ、正解というものはありません。
ただ、税務署から文句を言われないようにするための一応の方法はあります。それは、消費税の「簡易課税の経費率(みなし仕入率)を基準にする方法」です。
消費税には「簡易課税」という制度があります。消費税は、本来、売り上げたときに客から預かった「預かり消費税」から、仕入などのときに支払った「支払い消費税」を引いて、その残額を納付します。とはいえ、中小企業や個人事業主がそこまで計算するのは手間がかかりすぎるので、事前に申請すれば簡単な方法で計算することが認められます。その簡単な計算するときに使うのが、次の経費率です。
各事業の標準的な経費率(消費税の簡易課税より)
卸売業…………………………90% 小売業…………80%
製造業、建設業………………70% 飲食業…………60%
金融・保険業、運輸通信業…50% 不動産業………40%
サービス業(飲食業を除く)
この経費率は、全国の業者の統計に基づいて決められています。この数字を基準にしていれば、だいたい普通の業者並みの経費計上ができるということです。ここに挙げた数字のプラス数%程度の計上ならば、ほぼ大丈夫でしょう。たとえばネットの通販業であれば、「小売業の80%」が該当します。したがって、売上の80%くらいまでは経費を計上しても大丈夫となります。年商が1,000万円の場合、800万円くらいは経費に計上しても、そう問題視されることはないというわけです。
否認するのは税務署にとって高いハードル
概算で申告する方法は、税務署から否認されるおそれがあると前述しました。とはいえ、実際、税務署が否認するかというと、否認することは税務署側にとってもかなり高いハードルになります。
税金の申告というのは、納税者が自分で申告して自分で納めることをルールとしている以上、概算で申告も基本的に認められます。税務当局は、申告内容に間違いがあるときに限って、それを修正させたり追徴したりできます。
つまり、納税者が「自分の申告は正しい」という証明をしなければ申告が認められないのではなく、税務当局がその申告は正しくないという証明をしない限り、申告は認められるのです。
したがって、概算での申告でも、いったんは申告が認められます。そして、その申告に誤りがあったときにはじめて修正なり追徴なりが行われるのです。
税務署としては、概算で申告を否認しようと思えば、それなりの材料を用意しなければいけませんが、そもそも帳票類がほとんど残っていないのですか、材料を揃えることが非常に難しいのです。
儲かっている人が明らかに少ない所得で申告しているのならいざ知らず、それほど実態とかけ離れていない申告ならば、税務署としては認めざるを得ない、というのが現実的なところなのです。
概算で申告は、もちろん正規の方法ではありません。実行するかどうかは自己責任で判断してください。
まとめ
弊所は、レシート領収書保存が少ない無申告者等であっても調査通知後の事前自主修正期限後申告はすべきという考えを支持します。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します