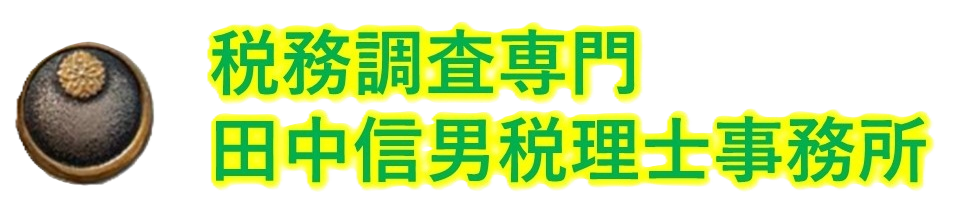平成30年3月7日裁決(平成30年納税者が支払った金員を譲渡費用と解釈して積極的に計上したことについて隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
(2023年11月14日作成)
当該ページの活用方法
・当該裁決の内容を理解する
・ご自身の税務調査に当てはまる、活用できそうなら、当該裁決内容及びあだ名を覚える
・ご自身の税務調査の場で活用させる
平成30年3月7日裁決のオリジナルのあだ名
平成30年納税者が支払った金員を譲渡費用と解釈して積極的に計上したことについて隠ぺい仮装を認めなかった裁決
当該裁決のまとめ
前提
・原文ではなく、弊所が内容を編集しております
・上記にもあるように、弊所の私見による内容の編集、見解を記述しているにすぎません。
裁決の内容、要約、編集
(1)事案の概要
・本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、農地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該農地で農業に従事していた弟に対して支払った金員を、当該農地の譲渡に要した費用として分離長期譲渡所得の総収入金額から控除して所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をした。
・税務調査の指摘に伴い、当該金員の一部を当該農地の譲渡に要した費用から減額する修正申告をした。
・その後さらに、原処分庁が、当該残金についても、当該農地の譲渡に要した費用とは認められず、譲渡所得の金額の計算上、控除できないとして、所得税等の更正処分をするとともに、請求人において、当該確定申告の際に譲渡費用に算入した金員全額を当該農地の譲渡に要した費用であるかのように仮装したとして、上記修正申告及び上記更正処分に係る重加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。
・請求人は、出生以後、別表1の順号5の建物(以下「d建物」という。)に居住し、高校卒業後は会社員として働いていたが、d建物からa市へ転居した。
・請求人の弟であるDは、出生以後、d建物に居住しており、中学卒業後は農業に従事していた。
・請求人の取得状況
◎相続により取得
●順合1~4及び順合5「d不動産」→Dへ贈与
●順号6及び7の土地を併せて「e各土地」→Dへ平成26年12月5日売却
●順号8及び9の土地を併せて「f各土地」
◎売買により取得
●順号10の土地を「g土地」
◎まとめ
●e各土地、f各土地及びg土地を併せて「本件各農地」
●d不動産及び本件各農地を併せて「本件各不動産」
・請求人は、Dに対し、本件各農地の「維持管理諸費用精算金(離農補償金)」として支払う。その内訳は、e各土地に係る維持管理諸経費5,935,000円及び離農補償金6,000,000円(以下、e各土地に係る維持管理諸経費及び離農補償金を併せて「e支払金」という。)並びにf各土地及びg土地に係る維持管理諸経費及び離農補償金2,000,000円(以下、f各土地及びg土地に係る維持管理諸経費及び離農補償金を併せて「f等支払金」という。)である。
・請求人は、Dに対し、平成26年12月5日に7,000,000円(以下「本件第1金員」という。)を、同月8日に6,935,000円(以下「本件第2金員」といい、本件第1金員と併せて「本件各金員」という。)を支払った。なお、本件第1金員に係る領収証(以下「本件第1領収証」という。)には「但 離農補償費」と、本件第2金員に係る領収証(以下「本件第2領収証」といい、本件第1領収証と併せて「本件各領収証」という。)には「但 離農補償金」とそれぞれ記載されている。
・請求人は、原処分庁に対し、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件各金員を離農補償金として譲渡費用に計上し、総収入金額から控除して、別表2の「確定申告」欄のとおり、法定申告期限までに平成26年分の所得税等の確定申告(以下「本件当初申告」という。)をした。
・原処分庁所属の調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)は、平成27年12月9日、請求人の平成26年分の所得税等に係る調査を開始したところ、請求人は、平成28年11月21日に、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、f等支払金を譲渡費用から減額して、別表2の「修正申告」欄のとおり、修正申告(以下「本件修正申告」という。)をした。
・原処分庁は、平成29年2月28日付で、本件各金員が、譲渡費用に該当しないとして、また、請求人が、本件各金員について、請求人とDの相続財産取得の件の解決金であるにもかかわらず、譲渡費用であるかのように仮装したなどとして、別表2の「賦課決定処分」欄のとおり本件修正申告に係る重加算税の賦課決定処分をするとともに、同日付で同表の「更正処分等」欄のとおり平成26年分の所得税等の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下、本件修正申告に係る重加算税の賦課決定処分と併せて、「本件各賦課決定処分」という。)をした。
・金額まとめ
◎(譲渡費用=)13,935,000=(5,935,000+6,000,000=e支払金)+2,000,000(f等支払金=平成28年11月21日の税務調査による修正申告の勧奨で減額して除外)
◎(譲渡費用=)13,935,000=7,000,000(第1金員)+6,935,000(第2金員)
・処分日←平成29年2月28日
・調査日←平成27年12月9日
・所得税の調査対象期間←平成26年分←法定申告期限平成27年3月15日←処分日から2年以内
・原処分庁は、以下のように主張している。
◎e支払金は、e各土地の事実上の使用貸借を解消するために支払われたものであり、e各土地の離農補償金ではない。
◎譲渡費用とは、資産の譲渡のために直接要した費用をいうところ、e支払金は、e各土地の離農補償金ではなく、e各土地の譲渡のために直接要した費用ではないから、e支払金は、譲渡費用に該当しない。
・請求人は、以下のように主張している。
◎請求人は、Dに対し、e各土地を貸し渡し、Dは、その対価として、請求人が所有する本件各不動産の固定資産税等の租税公課を、請求人に代わって支払っていたことから、e各土地の貸借関係は、賃貸借である(ただし、上記賃貸借は、農地法上の許可を受けていないので、いわゆるヤミ小作である。)
◎請求人は、Dとの間で、本件各不動産の貸借関係をはっきりさせるために話合いを行ってきた。そして、請求人及びDは、本件第1確約書及び本件第2確約書により、e各土地については、売却した上で、その売買代金の中から、e支払金を離農補償金として支払うことに合意した。以上のとおり、e支払金は、e各土地に係る離農補償金である
◎ヤミ小作に係る離農補償金を受け取った場合は、分離課税譲渡所得として課税されることからすると、ヤミ小作に係る土地の売却に際して離農補償金を支払った場合、当該離農補償金は、当該土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当すると解される。
(2)争点
・争点1(省略)
・争点2、e支払金は、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するか
・争点3、請求人は、平成26年分の所得税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装したか
(3)引用された最高裁判決判例、地裁判決
最高裁平成7年4月28日判決=オリジナル命名:最高裁平成7年積極的な隠蔽なしの無申告だが当初から過少申告の意図を外部からうかがい得る行動した判決の前半部分を引用したと明記されています。
(4)争点2の審判所の判断(e支払金は、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するか)
・e支払金が、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当するか判断するためには、まず本件貸借期間における請求人とDとの間のe各土地の貸借関係を検討し、当該貸借関係を基に、e支払金の譲渡費用該当性を検討するのが相当である。
・請求人とDとの間には、本件貸借期間において、少なくとも黙示の使用貸借契約が成立していたものと認められる。
・土地の使用貸借の場合、その利用権の経済的価値は、課税上、零とみるのが相当であるから、貸主である請求人が、借主であるDに対し、e各土地の返還を受ける目的でe支払金を支払ったとしても、e支払金は、課税上、e各土地の使用貸借に係る利用権の譲渡又は消滅の対価と認めることはできないというべきである。したがって、e支払金は、e各土地の譲渡のために直接要した費用に当たらず、また、e各土地の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用にも当たらないから、e各土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に該当しない。
(5)争点3の審判所の判断(請求人は、平成26年分の所得税等の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装したか)
・原処分庁は、要するに、請求人が、本件各金員について、離農補償金ではないため、譲渡費用にならないことを認識していたことを前提に、本件各領収証における本件各金員の名目を「離農補償費」又は「離農補償金」としたことが、請求人による隠ぺい、仮装と評価すべき行為である旨主張する。そして、原処分庁は、本件各金員が離農補償金ではないため、譲渡費用にならないという請求人の認識について、①請求人が、Dには本件各農地の農地法上の耕作権がないことを知りながら、本件各不動産の貸借関係についてのDとの紛争解決のために、本件第2確約書に署名した旨申述したこと、②請求人がDに持参した本件第1確約書には、本件各金員の一部の名目が土地経費及び礼金であると記載されていること、③請求人及びDは、本件各金員の名目を「維持管理諸費用精算金(離農補償金)」とする本件第2確約書に合意したことから認められる旨主張する。
・①についてみると、請求人が、Dに農地法上の耕作権がないことを知っていたとしても、そのことをもって直ちに、Dとの間の貸借状態解消のために支払った本件各金員が譲渡費用にならないことまで認識していたとはいい難い。
・②及び③についてみると、確かに、本件第1確約書には、本件各金員の一部の名目が土地経費及び礼金であると記載されており、また、本件第2確約書における本件各金員の一部の名目は、本件各農地の維持管理諸経費である。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、Dは、本件各不動産の処分を巡る請求人とDの話合いにおいて、本件各不動産に係る諸経費の清算を主張し、請求人は、これに応じなかったこと、請求人 は、本件第1金員を支払った際、Dから、「但 返済金(内金)」や「但 農業経費代(内金)」と記載した領収証を受け取らず、「但 離農補償費」と記載された本件第1領収証を受け取ったことが認められるところ、このような経緯によれば、請求人は、本件各金員の全てが離農補償金であると認識していたものの、本件各不動産に係る諸経費の清算を主張するDに譲歩して、本件各金員の一部の名目が土地経費及び礼金であると記載されている本件第1確約書やその名目が維持管理諸経費であると記載されている本件第2確約書に合意した可能性があるというべきである。そうすると、②及び③は、請求人が、本件各金員について、離農補償金ではなく、譲渡費用にならないと認識していたことを直ちに推認させるものということはできない。
・本件各領収証における本件各金員の名目を「離農補償費」又は「離農補償金」としたことは、請求人による仮装と評価すべき行為に該当するとは認められない。
(6)結果
所得税の調査対象期間←平成26年分←所得税の更正処分は適法であり、重加算税を取消す。
当該裁決のさらなる要約
・請求人が当初申告した譲渡所得の計算式は、売買代金○○○円-13,935,000円(※1、※2)
・※1(譲渡費用=)13,935,000=(5,935,000+6,000,000=e支払金)+2,000,000(f等支払金=平成28年11月21日の税務調査による修正申告の勧奨で減額して除外)
・※2(譲渡費用=)13,935,000=7,000,000(第1金員)+6,935,000(第2金員)
・平成28年11月21日の税務調査による修正申告の勧奨による修正申告の計算式は、売買代金○○○円-11,935,000円
・しかし、平成29年2月28日処分で、11,935,000円も譲渡費用に該当しないという処分及び譲渡費用であるかのように仮装したとして重加算税賦課処分をした。
・請求人とDは使用貸借であったので本件各金員は譲渡費用に該当しないとされた。
・しかし、本件各領収証における本件各金員の名目を「離農補償費」又は「離農補償金」としたことは、請求人による仮装と評価すべき行為に該当するとは認められない、としました。
弊所独自の考察
・弊所独自の視点
◎当該裁決は、当初申告は、申告済みでした。
◎当該裁決は、国税が納税者の隠ぺい仮装を主張したことはいいがかりである、と弊所が感じた事例です。なぜなら、納税者というのは当然ながら自身に有利な方法、解釈を選択して申告書を作成するところ、今回はe支払金が譲渡費用に該当するとしてチャレンジした申告でした。しかし当該チャレンジについて、領収書に明記された文言などを指摘して、隠ぺい仮装であると主張した原処分庁はいいがかりである、と感じたからです。
◎当該裁決は、取引を把握できるような資料が存在していたと解されます。
◎当該裁決において、請求人の調査への協力具合は、協力的であったと解されます。
◎当該裁決において、請求人の調査への虚偽発言は無かったと解されます。
・当該裁決から導いた弊所独自の重加算税賦課回避基準(あくまで私見であり一切の保証はできかねます)
納税者の解釈による積極的な経費計上について原処分庁が隠ぺい仮装を主張するような場合には隠ぺい仮装を否定することで重加算税を回避できる可能性があります(あくまで私見であり一切の保証はできかねます)
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年2月8日普段から簡単にできる究極の税務調査対策についてお伝えします
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します