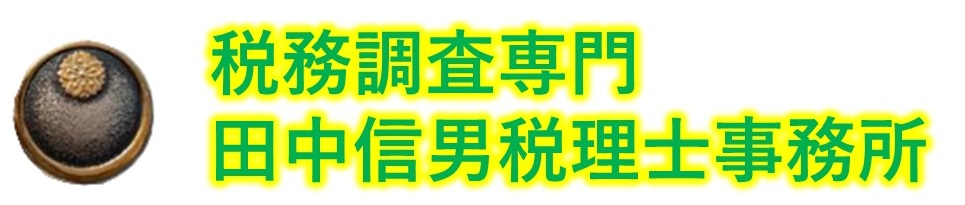重加算税賦課要件事実の立証責任と証明度について
(2026年1月22日更新)
結論
・重加算税賦課要件事実の立証責任も国税・課税庁・税務署が負っていると解されます。
・ただ過少申告加算税の免除規定である正当な理由の立証責任は納税者にあるとされています。
・また更正があるべきことを予知していたかどうかの立証責任は納税者にあるとされています。
・重加算税賦課要件事実の証明度については、ルンバール事件という最高裁判決における、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる、という考えを採用することが妥当すると解されます。
下記で詳細を記述します。
重加算税賦課要件事実の立証責任も国税・課税庁・税務署が負っていると解されます
立証責任についてはこちらのページをご参考ください。
また谷原書籍は下記です。
谷原誠「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」ぎょうせい(令和元年12月1日)p131-132より、
課税庁が重加算税賦課決定を行うには、法を解釈し、事実認定した上で、法法規に事実を当てはめることが必要です。そして、課税庁が重加算税賦課決定を行う際には、後日、不服申立や最終的には処分取消訴訟において敗訴しないようにしなければなりません。したがって、訴訟における事実認定に従って事実認定を行うことになります。
ところで、訴訟においては、主張立証責任という概念があります。これは、主張立証責任を負担する当事者が、法律上の要件(課税要件)に該当する事実を主張立証しなければならない。というものです。
要件事実の立証責任の分配については、判例では、法律要件分類説によるものが多いと言われています。法律要件分類説は、民事訴訟における立証責任の分配に関する通説です。行政処分の権利発生事実は行政庁が、権利障がい及び証明津事実は国民が立証責任を負うとする説です。取消しを求められた行政処分(更正)が法規を適用した行政処分であるときは、国が立証責任を負い、法規の適用を拒否した行政処分であるときは、国民が立証責任を負う、という説明もできます。
課税要件事実の立証責任は、納税者と課税庁とどちらが負担するかについて、最高裁判決は、所得税事案に関し「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決、月報9巻5号668頁)としており、課税要件事実の主張立証責任は課税庁にあるとしています。
以上から、重加算税賦課要件事実の立証責任も国税・課税庁・税務署が負っていると考えてよさそうです。
ただ過少申告加算税の免除規定である正当な理由の立証責任は納税者にあるとされています
谷原誠「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」ぎょうせい(令和元年12月1日)p133より、
国税通則法68条1項の重加算税は、過少申告加算税の賦課要件を満たすことを前提としていますが、過少申告加算税の免除規定である「正当な理由」の主張立証責任について、東京高裁平成18年1月18日判決(税務訴訟資料256号順号10265)は、「この過少申告加算税の例外事由である『正当な理由』の主張立証責任は、納税者にあるものと解すべきである」としています。東京高裁昭和55年5月27日判決同旨です。
また更正があるべきことを予知していたかどうかの立証責任は納税者にあるとされています。
谷原誠「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」ぎょうせい(令和元年12月1日)p133-134より、
また、同項(国税通則法68条1項)では「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではない場合」には重加算税を課さない旨規定しています。この「更正があるべきことを予知」していたかどうかについての主張立証責任については、東京地裁昭和56年7月16日判決(TAINS Z120-4832)「修正申告書の提出が更正があるべきことを予知されたものでないときに例外的に加算税を賦課しないこととした既定の趣旨からすれば、右の点については調査により更正があるべきことを予知して修正申告がされたものでないことの主張・立証責任が原告にあるべきである。」とし、納税者に主張・立証責任があるとしています。
更正の予知についてはこちらのページをご参考ください。
重加算税賦課要件事実の証明度
立証責任を負担する者はどの程度証明すれば立証したことになるのかという、証明度の問題があります。
・谷原誠「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」ぎょうせい(令和元年12月1日)p134-135より、ルンバール事件判決(最高裁昭和50年10月24日判決、民集29巻9号1417頁)を紹介しています。
・「証明度」については税法裁判に限らず、法全体の論点としている壮大な論点であるため、議論をするには広すぎることから、弊所は税理士谷原誠が提唱するルンバール事件判決の指す証明度をそのまま利用することといたします。
ルンバール事件判決における事実認定の証明度のルールは、以下とされました。
①立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない
②経験則に照らして全証拠を総合検討する
③因果関係については高度の蓋然性を証明する
④通常人が疑を差し込まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
したがって、税務調査において、重加算税の指摘を受けた際には、課税庁が主張する重加算税賦課要件事実が、収集された証拠により、この証明度に達しているか吟味する必要がある、と記述されています。
この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
-
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
- 2026年1月7日隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します
- 2026年1月7日事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します
- 2026年1月7日税務調査対策として消費税原則課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します